
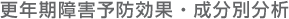
イソフラボン
女性ホルモンに似た作用で不足したホルモンの働きを補います
豆腐の材料である大豆に含まれるイソフラボンは、エストロゲンと似た構造をしていることから、エストロゲンと似た働きをする女性ホルモン様作用があります。イソフラボンは大豆の色素であるフラボノイドの一種で、体内で女性ホルモンが不足しているときには特に女性ホルモン様の作用を強く発揮するようになります。
たんぱく質
肝臓を活発化し性ホルモンの合成を促します
食品に含まれるたんぱく質を摂ると胃で消化されてアミノ酸に分解され、小腸から吸収されて血液中に入ります。そして、肝臓で体に必要なたんぱく質に組み立てられていきます。ホルモンは、たんぱく質でできているため、アミノ酸バランスのよい豆腐のたんぱく質はホルモンを増やすのに役立ちます。エストロゲンをはじめとした性ホルモンは肝臓でも合成されます。性ホルモンの原料の合成を促すためには肝臓の働きを高めることが大切です。肝臓そのものの材料であり、肝機能を高めるのに欠かせないたんぱく質の補給は、性ホルモンの増加につながります。
ビタミンE
ホルモン分泌を促進して更年期障害の症状を軽減します
ビタミンEの化学名はトコフェロールといって、生命の源を意味します。ビタミンEは男性ホルモン、女性ホルモンの分泌を促進する作用があり、たとえば女性ホルモンの分泌が低下しているときには特に分泌を盛んにしてくれます。また、ビタミンEは過酸化脂質を分解して血行をよくする作用があり、更年期障害の症状として見られる頭痛、肩こり、冷えなどの改善にも効果があります。
カルシウム
ホルモンの分泌を促進更年期のイライラを改善します
ホルモンの分泌に関わるミネラルで、カルシウムが不足するとホルモン分泌が低下しやすいことが知られています。また、カルシウムは、神経伝達物質の流れを補助する働きをしているので、更年期のイライラ感などの改善にも必要です。カルシウムは厚生労働省の『国民栄養調査』で必要量に対して10%ほども不足しています。肉類や加工食品、清涼飲料水にはリンが多く含まれていますが、リンが血液中に多くなるとカルシウムの排泄量が増えます。豆腐は大豆製品の中ではカルシウムが豊富なので、豆腐を摂ることはカルシウム不足解消の手助けになります。
マグネシウム
神経の興奮を鎮めてストレスを解消します
神経の興奮を鎮める作用がありますが、ストレスがかかるとマグネシウムの消費量が高まります。マグネシウムの摂取はストレスの解消に役立ちますが、肉や加工食品、清涼飲料水に多いリンはマグネシウムの吸収をさまたげるので、これらの食品を食べるときにはマグネシウムの補給が欠かせません。
サポニン
肝機能を向上させてエストロゲンの分泌を高めます
過酸化脂質ができるのを抑え、肝機能を高める作用があります。肝臓はコレステロールを製造する働きがあり、肝機能の向上は性ホルモンの材料であるコレステロールを増やして、エストロゲンの分泌を高めるようになります。



